「ちゃんとしなきゃ」「まわりに合わせなきゃ」って思いすぎて、 気づけば自分の気持ちが見えなくなっていませんか?
本当は、もう少し“わがまま”でいいんです。
誰かに迷惑をかけることじゃなくて、自分に正直でいること。
1000年前の清少納言は、それを実践して生きていました。
彼女の生き方は、今の私たちにこそ必要な“自分軸”のあり方を教えてくれます。

自分軸を見失いそうなときに

私はアクセサリー作家として活動しています。
小さい頃からものづくりが好きで、その気持ちにずっと正直でいたくて、この道を選びました。
始めたころは、販売の知識もデザインの基礎もゼロ。会計管理だって初心者。
「無理じゃない?」と周りから思われてもおかしくない状況でした。
それでも心の中にあったのは、ただ一つ。
「私は、これがしたい」という思い。
その小さな声に耳を傾けてきたからこそ、今も続けられているのだと思います。
清少納言の生き方には、そんな“自分軸”を育てる大切なヒントが詰まっています。
清少納言って、どんな人?
「春はあけぼの」で始まる『枕草子』。
この美しい随筆を残したのが、平安時代の宮廷女流作家・清少納言です。
控えめが美徳とされた時代に、彼女は堂々と、 「これは美しい」「これは心地よい」「これはにくい」と、 自分の感覚を言葉にしました。
 ピヨ
ピヨどうしてそんなにハッキリ言えたの?



空気を読んで黙るのが当たり前の時代だったのにね。すごいよね。
枕草子を読んでいると、清少納言の率直さに思わずクスッと笑ってしまいます。
1000年前の彼女が、「これってあるよね」って笑って話しかけてくれているようです。
清少納言のすごさは“自分軸”
清少納言がすごいのは、他人軸よりも自分軸を選んだことです。
宮廷という“空気を読む”のが必須の場所で、 それでも自分の感じたことを信じて表現しました。
・誰かの仕草に覚える違和感
・自然のうつろいに見出す美しさ
・なかなか口にできない人間の本音 など
小さな感情を見逃さず、「これが私」と大事にできたんです。
たとえば『枕草子』には、やわらかな“ときめき”も、率直な“にがて”も、そのままの言葉で残っています。
老いたる女の、腹高くて歩く。若き男持ちたるだに見苦しきに、異人のもとへ行きたるとて、腹立つよ。
出典:清少納言 角川書店編ビギナーズ・クラシックス日本の古典『枕草子』/角川ソフィア文庫
(年とった女が、大きなお腹を抱えて歩いているの。いい年をして若い夫を持っているのさえみっともないのに、その男がほかの女の所へ通っていると言って腹を立てるなんて。)
清少納言のまなざしの鋭さに思わず「そこまで言う!?」と思ってしまいます。
身分や年齢で生き方が縛られていた時代だからこそ、痛烈な言葉が向けられたのでしょう。
一方で、こんな場面も。
うつくしきもの 瓜に描きたる児の顔。雀の子の、鼠鳴きするに、躍り来る。二つ三つばかりなる児の、急ぎて這ひ来る道に、いと小さき塵のありけるを目ざとに見つけて、いとをかしげなる指にとらへて、大人などに見せたる、いとうつくし。
出典:清少納言 角川書店編ビギナーズ・クラシックス日本の古典『枕草子』/角川ソフィア文庫
(かわいらしいもの。ウリに描いた子供の顔。スズメの子がチュッチュッというと跳ねて来る。二つか三つの幼児が、急いで這って来る途中に、ほんの小さなごみがあったのをめざとく見つけて、ふっくらと小さな指でつまんで、大人などに見せているしぐさ。)
かわいらしいと感じた一瞬を、まるで日記のように素直に書き残しているんですね。
また、こんな心理も綴っています。
人の上言ふを腹立つ人こそ、いとわりなけれ。いかでか言はではあらむ。我が身をば差し置きて、さばかりもどかしく言はまほしきものやはある。されど、けしからぬやうにもあり、また、おのづから聞きつけて、恨みもぞする、あいなし。また、思ひ放つまじきあたりは、いとほしなど思ひ解けば、念じて言はぬをや。さだになくは、うち出で、笑ひもしつべし。
出典:清少納言 角川書店編ビギナーズ・クラシックス日本の古典『枕草子』/角川ソフィア文庫
(人の悪口を言うのを怒る人は、わけがわからない。どうして言わずにいられようか。自分のことは棚に上げて、これほどじれったく言いたいものが他にあろうか。でも、あまり感心できないことだろうし、その上、当人が自然聞きつけて恨んだりするから、困ったもの。また、嫌いになってしまえない人のことは、気の毒だと大目に見て、我慢して言わない。そうでもなければ、すぐ言い出して笑いものにしてしまうだろう。)
「悪口はいけない」とわかっていても、つい口にしたくなる人の気持ちに、思わずクスッとしてしまいます。
1000年前も今も人の心理って変わらないんだなあ、と親近感さえわいてきます。



ちょっと辛口すぎない!?



でも…読んでるとなんか笑っちゃう。
当時は控えめが美徳とされた時代。
けれど彼女は、自分の感覚を素直に堂々と書き残しました。
その姿勢はやがて「随筆文学の祖」とまで呼ばれ、紫式部の『源氏物語』と並んで日本文化を代表する古典に数えられるようになります。
つまり清少納言が“自分軸”で表現したからこそ、『枕草子』は1000年を越えて今も読み継がれ、私たちに「自分に正直でいていいんだよ」というメッセージを届けてくれているのです。
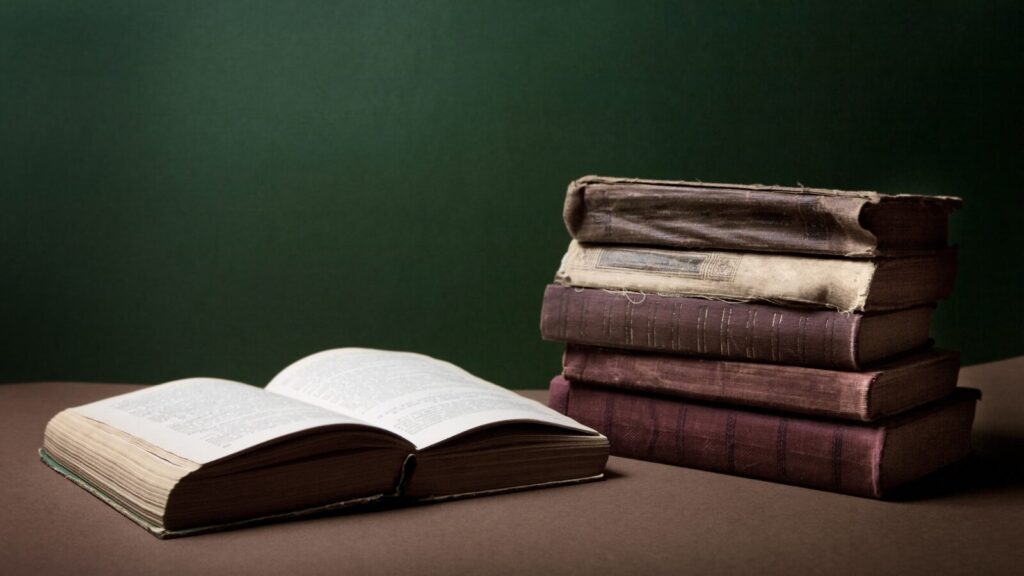
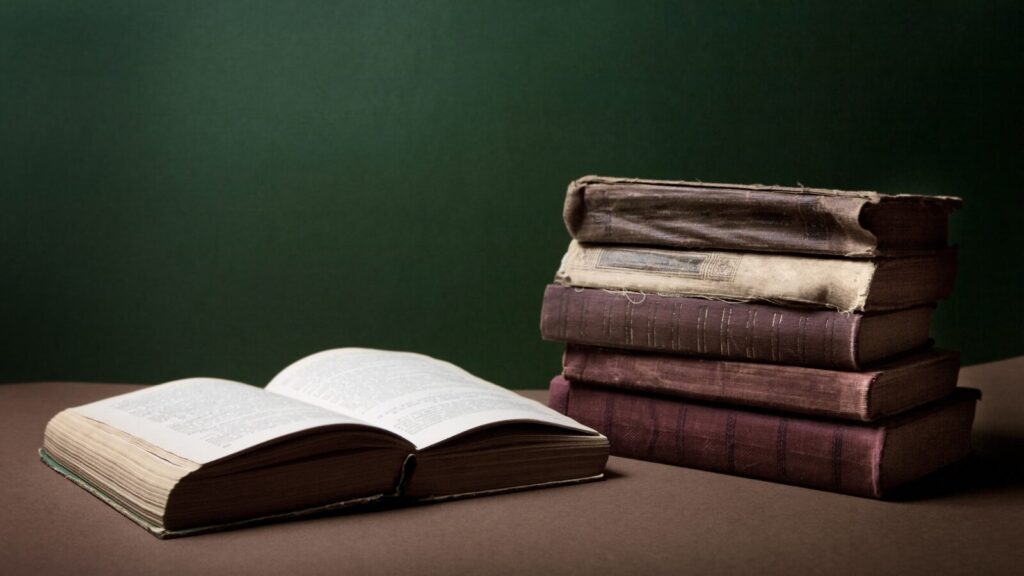
自分軸がある人の特徴
“自分軸がある人”は、周りを無視して好き勝手に振る舞う人ではありません。
「私はこう思う」と言える人であり、同時に相手の気持ちも受け止められる人です。
他人軸でばかり生きると、やさしさのようでいて、実は自分をすり減らしてしまうことがあります。
自分に正直でいられる人こそ、ブレずに人にやさしくできる。



自分をたいせつにすることは、誰かをたいせつにすることにもつながるんだよ。
私も以前は、ぶつかるのが嫌で、周囲に合わせすぎていました。
そのせいで、気づけば心がすり減っていたんです。
でもあるとき、自分の気持ちを素直に言ってみたんです。
意外にも、相手はちゃんと受け止めてくれました。
そこから少しずつ、自分の気持ちを後まわしにせず、正直に言えるようになりました。
すると不思議なことに、人との関わりも穏やかになり、むしろ「自分軸がある人」として信頼してもらえるようになったんです。
清少納言に学ぶ、自分軸で生きる力
“自分軸で生きる”とは、「私はこう感じた」「私はこう在りたい」という気持ちに、素直に耳を傾けること。
つまり、自分に正直に生きていいということなんです。
清少納言のように、自分に正直でいることは、やさしさやしなやかさにつながり、やがて誰かを照らす光にもなるのだと思います。
たとえ小さな声でも、「これが私だ」と思える気持ちを大切にできたら、毎日が少しずつ心地よく変わっていくはずです。



わたしも、“自分に正直”でいいんだよね。
今日できることー小さな“こうしたい”を積み重ねる
・朝、窓を開けて空を見上げてみる。空の色や空気を感じる
・服を選ぶとき、「自分が気分よくいられるか」を大事にしてみる
・その日食べたいものを、自分に正直になって選んでみる
自分の”好き”や”心地よさ”に目を向けてみる。


自分軸をたいせつにして生きるために
少しだけ“わがまま”になってもいい。
それは、誰かを困らせることじゃなくて、自分に正直になることだから。
清少納言の言葉は、1000年経った今も、 「あなたはあなたの感覚を大切にしていいんだよ」と教えてくれます。
今日も、自分の心の声に耳をすませてみてくださいね。
比べなくてもいい、焦らなくてもいい。



そのままのあなたに◯をあげてくださいね。
ほんのひとときでも、心がゆるむ時間になっていたらうれしいです。
また何かのときに、ふとこの記事を思い出してもらえたら。




コメント